秋田駒、森吉山から帰っても、大人の休日倶楽部パスがまだ使えるので、一日休んで、長野に行くことに。松代の真田関連を訪ねようかと思ったのですが、雨模様。そこで、丁度、駅からハイキング「善光寺とお地蔵様をめぐる」があったので、善光寺にしました。長野駅観光案内所で次回の為に、松代の資料をいただく。「街あるき」のイベントにもあったので、パンフレットを貰って、出発。
まずは西光寺。かるかや上人と石童丸親子の物語が伝わる「絵解き」のお寺です。「絵解き」とは文字の読めない人の為に絵でもって説教・唱導(仏の道に導くため、教えを説くこと)を目的とする、宗教者による絵画を用いた文芸・芸能です。
口演者の当意即妙な語りが、聴衆を引き付ける絵解きの多くは、現在、寺社を中心 に伝えられてきました。 |
 |
 |
| 西光寺 |
刈萱上人と石童丸の像 ↑マウスオン
修行中の身で親と名乗れなかった。 |
 |
 |
| 大師堂(園通殿) |
左から千里御前、刈萱上人、石童丸の墓 |
 |
 |
芭蕉句碑
「雪つるや 穂屋のすすきの刈残し」 |
六地蔵
六道、それぞれのお地蔵様 |
 |
 |
| リンゴの花とリンゴのマンホール |
丁目の標識 |
 |
 |
| 左右の道は以前、川でした。その中州に建てられたのが栽松院です。 |
 |
 |
栽松院
中洲にあったので、「しまんりょう」と呼ばれた。 |
本堂 |
 |
 |
| 赤色の子育て地蔵 |
嶋の天神 |
| |
|
| 参道は広い。両側に色んなお店があります。 |
 |
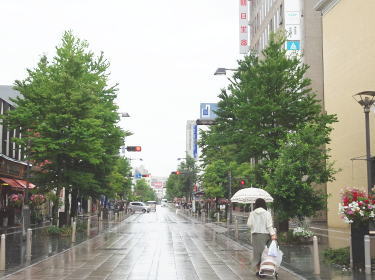 |
| 長野オリンピックの聖火台。 ↑マウスオン |
善光寺ゆかりの桂の並木 |
 |
 |
西方寺
1192年、法然上人が開創 |
紫雲石
いずれよりか現れた紫の石の上に善導大師の像が乗っていた。 |
 |
 |
立体曼荼羅、チベット大仏
2012年、ダライ・ラマによって開眼。 |
立体曼荼羅由来の碑 |
 |
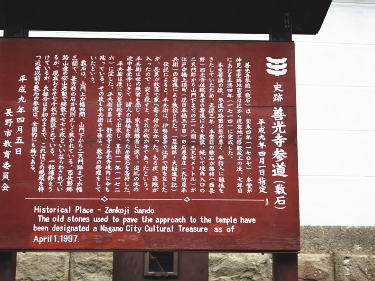 |
| 敷石は1707年から7年かけて完成。7777枚といいならわされている。 |
| |
| 仁王門手前左に大本願があります。善光寺創建642年から歴史を共にしてきた尼僧寺院。浄土宗。 |
 |
 |
| 本誓殿(本堂) |
唐門 |
 |
 |
芭蕉句碑
「月影や 四門四宗も 只一つ」 |
家光の御台所、関白鷹司の二女孝子を供養する地蔵。 |
 |
| 仁王門 1752年建立されたが、二度焼失。今のは1918年再建 |
 |
 |
| 仁王像も立派です。わらじを奉納するのは健脚を祈願したもの。 |
 |
 |
| 旧如来堂跡地蔵尊 |
釈迦堂
973年越後の浜で漁師が見つけた涅槃像を安置 |
 |
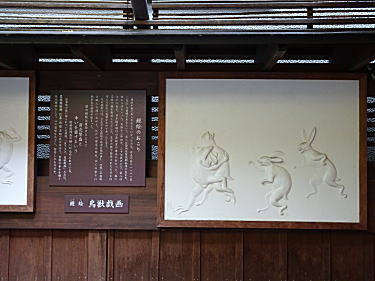 |
| 花が池。善光寺七つ池の一つ |
鏝絵 伊豆の長八という左官が始めた。
魔除け、商売繁盛などのご利益がある。 |
 |
 |
駒返り橋。
源頼朝が参詣時、馬の蹄が石橋の穴にはまり、
馬を返して徒歩で入った。 |
1722年造立の延命地蔵。
「八百屋お七のぬれ仏」とも呼ばれる。 |
 |
| 山門(三門)1750年建立。5羽の鳩が隠されている「善光寺」の額。重文 |
| |
| 立派な山門です。登れるというので、入ってみました。料金500円 |
 |
 |
| 正面は参道 |
大勧進 |
 |
 |
| ?? |
経蔵 重文 |
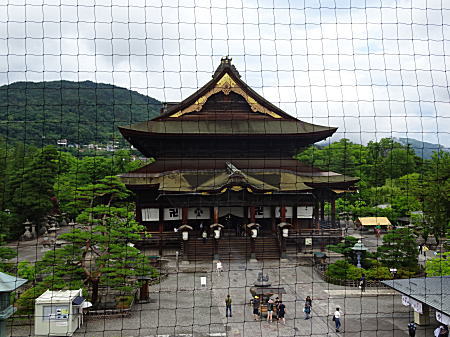 |
| 本堂。 ↑マウスオンは地上からの本堂。 |
| |
本堂に入り、内陣で参拝、恐る恐る、お戒壇めぐりをしました。
外に出て境内を散策。 |
 |
 |
| シナノキの花 |
オオカメノキの赤い実かな? |
 |
 |
| 変った色の紫陽花 |
杏でしょうか? |
 |
 |
| 梵鐘は1667年鋳造。鐘楼は1853年の再建。 |
千人塚。百姓一揆で亡くなった人の供養塔 |
 |
 |
| 徳川家大奥関係者の供養塔 |
戊辰戦争から第二次世界大戦までの戦争
で亡くなった人を祀る仏式霊廟 |
 |
 |
| ちょっとした紫陽花の庭 |
経蔵 1759年完成。 |
 |
 |
輪蔵
鉄眼黄檗版一切経が納められています。 |
輪廻塔
車輪状の石を回すと様々な苦悩を抜け出せる。 |
 |
 |
| 仏足石。 お釈迦様の足跡を石に刻んだもの。 |
 |
 |
| 石造宝篋印塔 1397年の古いもの。 |
大勧進
善光寺の寺務をつかさどる天台宗の寺 |
| |
|
| そろそろ、帰路につきますが、行きに通り過ぎて立ち寄れなかった所を訪ねます。 |
 |
 |
十念寺
建久年間の創建で源頼朝公を開基としています。 |
出世大仏
高さ5mの阿弥陀仏坐像 |
 |
 |
| 徳本上人名号碑 |
六地蔵 |
| |
|
| 行きに迷って分からなかった所にも寄ります。 |
 |
 |
| 延命庵 |
目の病に御利益のある「経読み地蔵」 |
| |
|
| すっかり、お昼を過ぎてしまいました。「街あるき」のパンフレットにあるお蕎麦やで信州そばをいあtだきました。天ぷら3点がおまけです。和菓子屋でお土産に和菓子を買うと、一個おまけ。パンフレットのおかげです。 |
 |
 |
| 長野駅前の如是姫像 |
JR長野駅。全体が撮れなかった。 |
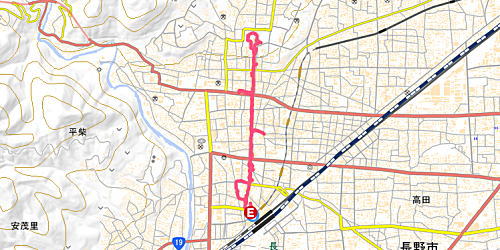 |
| 6.59Km 4:32(食事を含む) |