平成、令和にまたがる10連休も今日を含めて、あと2日。今日は「駅からハイキング」の「こくぶんじの恋と歴史と文化をめぐる春の探訪」に行きます。2人です。半分くらいは既に歩いた所ですが、半分は知らない所です。
国分寺駅の駅ビルも大きい。駅の北側から歩き始めます。 |
 |
| 恋ケ窪東遺跡柄鏡形敷石住居跡 |
| 縄文時代の中期末から後期。住居の床面に石(礫)を敷いてあります。この住居跡は、出入口部が突出した様子から「柄鏡形敷石住居跡」と呼びます。 |
 |
 |
| 説明板 |
ガードレールは勾玉? |
 |
 |
| JRの線路と右側は西武線の線路 |
散策マップやベンチがあります。↑マウスオン |
| 西武線の線路をくぐって進みます。 |
 |
 |
| 姿身の池。鎌倉時代、遊女たちが鏡代わりに姿を池に映していたという伝承が名前の由来。遊女の夙妻太夫が武将・畠山重忠を慕って 身を投げた池という「恋ケ窪伝説」が残ります。 |
 |
 |
| 道端の石仏 |
汚水マンホール サツキの花の模様 |
 |
 |
| JR西国分寺駅を過ぎます。 |
日本芸術高等学園 |
 |
 |
| 東山道武蔵路跡 |
古街道の地図 |
 |
 |
| 大きな樹 残してあります。 |
国分寺史跡めぐり案内図 |
 |
 |
| 国分寺薬師堂 |
仁王門 ↑マウスオン |
 |
国史跡武蔵国分寺跡。奈良時代中頃の天平13年(741)、聖武天皇は仏の力で国を安定させるために、諸国に国分寺の建立を命じました。武蔵国では、都と国府(現府中市内)を結ぶ古代官道「東山道武蔵路」沿いの東に僧寺、西に尼寺が計画的に配置されました。
武蔵国分寺跡は、全国の国分寺跡と比べても規模が大きく、その歴史的重要性はつとに認められており、大正11年に国指定史跡に指定されています。
講堂跡、金堂跡や、講堂、金堂間の通路、幢竿遺構などが再現されています。 |
 |
 |
| 講堂跡の縁に腰かけてお弁当を食べようとしていたら、「その下に当時の瓦があります」と言われ、びっくり!右の写真 |
 |
 |
| 国分寺楼門 江戸時代の建築 |
国分寺 ↑マウスオン |
| 境内に万葉植物園があります。 |
 |
 |
| ジャケッツイバラ ↑マウスオン |
タツナミソウの白花 |
 |
 |
| ヤマアイ |
オモダカ |
| お鷹の道湧水園に入ります。史跡の駅おたカフェで入場券を買います。 |
 |
 |
| 代々国分寺村の名主であった旧本多家住宅の長屋門を見学。蔵も残っています。 |
 |
 |
| エビネ |
ムサシアブミ |
| 武蔵国分寺資料館も見学して、用水沿いのお鷹の道を歩きます。 |
 |
 |
民家の植木ですが、どこかで見たことあるのですが、名前が出てこない・・・
ギョリュウ(御柳)でした。 |
 |
 |
| 真姿の池湧水群 |
 |
 |
| 用水にはカラーの花が咲いています。 |
 |
 |
| 不動橋 ↑マウスオン |
石橋供養塔 |
| 殿ヶ谷戸公園の前を過ぎ、JRの殿ヶ谷戸立体をくぐって、北へ向かうと・・・ |
 |
 |
| 歩道のマンホールの蓋にはペンシルロケットの説明がありました。 |
 |
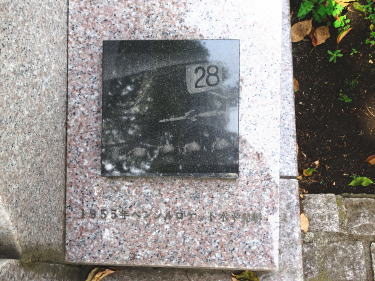 |
| 日本の宇宙開発発祥の地顕彰碑 ↑マウスオン |
 |
 |
| ホームラン756号世界記録達成記念碑 |
早稲田実業高校 |
 |
 |
電車開通記念碑
明治22年(1889年)に、新宿・立川間で開通した甲武鉄道(現在の中央線)が政府に買収され、その後大正11年に国分寺駅まで電化が進み、電車が通ることになったのを記念して、同年11月21日に建てられた碑です。 |
ぶんバス
国分寺市のコミュニティバス |
| 国分寺駅でアイスでも食べようとさがして、やっとジェラードのお店を見つけて、ほっとします。 |
 |
| 7.2Km 4:18(休憩、見学含む) |
|
|